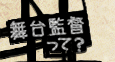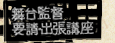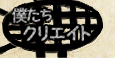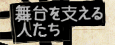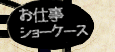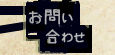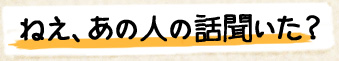| |
 |
金一浩司 クリエイト大阪創立者
山川啓介 作詞・構成家
大橋誠仁 クリエイト大阪創立当時よりのメンバー
長野真梧 クリエイト大阪代表取締役社長 |
|
| ●音楽との出会い |
| |
金一 |
「高校時代は野球部だった。その時、ピッチャーで4番バッターだった友人の家にレコードがたくさんあって、彼の家でSP盤などのアメリカ音楽をよく聴いていた。音楽に関してはその影響が大きいと思う。コンサートを生で見たのは、当時レコード会社などがやっていた『歌の大行進』という歌手をたくさん連れてきて歌わせるものだった。」 |
| |
山川 |
「大学に行くまでは長野にいた。長野には、大阪と違って歌手が来ない。長野は標高が高いのでラジオがよく入るので、ラジオから流れてきたアメリカポップスを聴いていた。その中にいいなと思う歌があった。それで調べたみたらミュージカルナンバーだった。当時は文学青年が三分の一、演劇青年が三分の一、音楽青年が三分の一。だからミュージカルに進んだ。」 |
| ●二人の出会い |
| |
山川 |
「ボクは学生の頃から作曲家のいずみたくさんが主宰者だったオールスタッフで、作詞をやらせてもらっていた。オールスタッフは、当時渡辺プロなどがテレビを中心にしたアーティスト展開をしていたのに対し、そのエネルギーをステージに注いだ。由紀さおり、ピンキーとキラーズなどたくさんの歌手をかかえていたが、それをコンサートやリサイタルで展開をしていた。そのステージは、日本最高峰のスタッフを揃えてやっていた。大学でミュージカル研究会にいて、脚本を書き舞台監督をやっていた自分は、アメリカかぶれで生意気だったが、それらの仕事に加わったことで、本当のプロのすごさを知った。ある時、吉永さゆりリサイタルがあり演出家の藤田敏夫さんに、訳詞をやらせてもらう機会があった。そのリサイタルの舞台監督が金一さんだった。」 |
| |
金一 |
「大阪労音にいた時に、オールスタッフと大阪労音が新しいことをやりたいという発想で一致した。そこでオールスタッフとのつきあいがはじまった。その頃は、この人とやってみたいと思う作家に、構成や演出を依頼できた。五木寛之、寺山修司そのほかたくさんの作家陣に依頼をした。失敗作もたくさんあったが・・・・。」 |
| |
山川 |
「当時はステージだけで食っている構成家はいなかった。ほとんどがテレビ出身者。ステージだけでやっていたのは藤田さんが最初だ。舞台監督も脚本家が舞台監督といってやっていた時代だったから職種として確立していなかった。座付き作家や、座付き舞台監督しかいなかった時代に、藤田さんがフリーの構成家になった。同じように、フリーの舞台監督のはしりだったのが金一さんだった。」 |
| ●若いときの苦労 |
| |
山川 |
「当時のスケジュールはめちゃくちゃで、無理なスケジュールの中で書き続けなければならなかった。ほめられてその気にさせられてなんとか無い力をふりしぼれた。藤田さんと飲んだ時、『自分の書いた物を書き直されていやな気分になっているだろうけど、三十才過ぎたらどこへ行っても通用するから、それまで頑張れ』と言われた。永六輔さん、朝倉摂さん、和田誠さん・・・みんながほめてくれた。それが、現在の自分につながっている。人はほめられて成長をする。だから自分も若い人はいいところを見つけてほめるようにしている。」 |
| |
金一 |
「藤田さんがいなければ、現在の自分はないとは思っているが、当時は怖かった。
本番が終わったらもう絶対に仕事をしないといつも思っていた。しかし、それがあったから演出家の言うことは、なんとかしてあげようという姿勢ができた。実は藤田さんが自分を怒ることによって、舞台全体の空気を引き締めようとしている事がわかったのは、だいぶ後になってからだった。それが、わからないと自分だけ怒られているような気になってしまう。演出が出来るということは、自分の美意識をどこまで貫きとおせるかということだ。演出家がわがままでなければならないという事は、その美意識を貫くためのものなのだ。」 |
| |
山川 |
「自分も当時の苦労があるから、降りると決めるまでは、どんなことをしても公演がうまくいくように努力し頑張る、我慢するとう事ができるようになった。」 |
| ●演出家と舞台監督と制作の違い |
| |
山川 |
「演出家と舞台監督の違いというのは、政治力だと思う。舞台監督は調整能力はあっても政治力があってはダメだと思う。クリエイト大阪に財産として残っているのは、制作的なことまでわかって仕事をするということだと思う。」 |
| |
大橋 |
「金一さんと一緒に仕事をして、舞台監督はなんのためにいるのかというのを学んだ。舞台監督と制作は疑似職ではない。他のセクションの仕事の範囲を尊重し、それを意識することによって自分の仕事が何かを考えるという習慣をクリエイト大阪の現場の空気の中で教わった。」 |
| |
山川 |
「舞台監督のひとつの仕事は調整役でもあるが、出演者側かスタッフ側かということで言ったら、スタッフの代弁者であるべきだと思う。出演者についたら、仕事を放棄していることになる。二十数年前に、ブロードウェイで見たミュージカルで、舞台監督が袖でスコアを見ながらすべてにキューを出している。舞台監督とはこれだと思った。演出家の物理的な代行者なのだ。舞台というのは、ほっといても上演はできるが、何かあった時にたちいかなくなる。調整役であり、制作の細部にわたり目がいきとどき、なおかつ出演者のケアをして、最終的にはスタッフの代弁者でなければならない。それをできるのが、金一という人だ。」 |
| ●コンサート作り |
| |
山川 |
「ボクは思想以前に完全にエンターテイメントを作りたかった。完全にエンターテイメントとは、完全に楽しいものということ。そこに社会がどうこうという思想を入れず、おもしろいものを作るのが目標だった。藤田敏夫さんの構成は歌手がしゃべらない。それがスタイルなのだと思う。それをボクは音楽力学と呼んでいる。それまで曲を並べて司会者がいて名前だけの演出がいるというステージに、アメリカ方式でステージ作りを行った。特に日本のステージに文学を持ち込んだ功績は大きい。自分は、歌手がごくごく普通にしゃべるだろうと思われることを書くというのが理想だが、音楽だけを積み重ねることによる音楽力学で客を感動させるのは別の意味での理想でもある。」 |
| |
金一 |
「構成という仕事は、皆無にちかくなっているが、今後はどうなのだろう。」 |
| |
山川 |
「構成は、その歌手がアドリブでしゃべっているのだと感じさせつつ、実は自分のドラマ作りにしたがって、歌の説明をするのでもなく、日常を語るわけでもなく、客にそのナンバーを味わってもらえるようにするという仕事。しかし、そういうコンサートの作り方は終わったと思う。金一さんや自分が体験してきたスタッフの組み方、作り方は終わった。時代だと思う。変わるべきだし変わってゆくと思う。そのことは、まったく悪いとは思わない。たとえていうなら、ステージの仕事は単行本で、テレビは雑誌だと思う。本を開いたら最後の一頁まで読ませるのが仕事。テレビは、どこから読んでも楽しいものを作る。そこに違いがある。それが、いい悪いの問題ではない。ただ、今のステージが雑誌に近づいているのも事実。」 |
| |
長野 |
「今は、構成ということでいえば小さくなっている。これを変えるには、やはりその専門家がいて作ってゆくスタイルに戻る必要もあるのではないか。」 |
| |
山川 |
「ただ、その必要性をだれが認めてくれるかというのが問題だ。」 |
| |
金一 |
「それは違うという意見もあるが、誰が金を払ってくれるかというのは現実問題としてある。」 |
| |
山川 |
「自分がなんでこの仕事をできたかというと、ステージ以外に作詞という仕事で収入があったからだ。現実問題として、ステージの構成で生活を維持できるだけの収入は得られない。これが、解決されなければ見よう見まねで放送作家や演出家などが構成をやって終わりという事になってしまう。」 |
| |
金一 |
「優秀な作家というのは、コンセプトを読んだだけでイメージが沸き、そこにお金を払ってもいいと思わせるものだ。しかし、誰がそれにお金を払うか、誰が必要としているかという問題だ。」 |
| |
大橋 |
「きちんと投資をする人がいる。それが大事なことだと思う。」 |
| |
山川 |
「バーブラストライザンドの最後のステージ、これが自分がやりたかった構成の理想だが、ぜひこれを見て欲しい。メディアミックスなどでペイするように出来てはいると思うが、構成者がいて舞台監督がいて音楽監督がいてとんでもなくスタッフにお金がかかっている。これは、なまじな舞台監督ではつとまらない。」 |
| |
金一 |
「これからは、そういうスタッフの必要性があるのだろうか?」 |
| |
山川 |
「アメリカでもそういう時代は終わっているのではないだろうか。」 |
| |
長野 |
「日本と確実に違うのは、メディアの問題があると思う。日本はテレビや映画というメディアがあり、その作家演出家がステージに入ってくるというのが主流。」 |
| |
山川 |
「しかし舞台監督というのは、出演者と客と同じ空間と空気と時間をを共有することにはプロであって、複製を作ることはプロではないと思う。同じように、映像を通した感動を作るということと、ホールという同じ空間を使って感動を作るとうのは別の問題だと思う。」 |
| |
長野 |
「今のステージは演出面で、ビジュアルが中心になってきている。全体のステージシーンをビジュアルの人が決めるようになってきている。」 |
| |
山川 |
「自分は、照明の吉井澄雄さんなどが作ったサス一本をどうつけるか消すかという物語があるビジュアルがいいと思う。」 |
| |
大橋 |
「今でも、最新の照明を使って、同じような演出をする人もいるが、正直全体のレベルは低い。ストイックに第三者が判断をすることが大事ではないか。」 |
| |
金一 |
「今は新しい歌をやろうとするが、他人の歌を歌うという風潮は、日本にないのだろうか?」 |
| |
大橋 |
「新しいアルバムをつくって、全曲やってというのが普通になっている。客は、それを聴きに来ているわけではない事も多い。あの曲を聴きたいという客の思いは別にある。 そいう意味では、構成という第三者の目が必要だと思う。これまで不要だという事で切り捨ててきたから、構成と言われても「何それ」ということになる。」 |
| |
長野 |
「昔は、歌を出すのがたいへんだったから、曲数が足りない。それをカバーするためにシチュエーションが必要だったということがある。今は、アルバムをすぐに出せる。すると、コンサートに必要な曲数が揃ってしまう。そいう事もあるのでは。しかし、十数年後にはまったく残っていないということにならないか。」 |
| |
大橋 |
「ただ、プロとして長く続けている人をみると、自分の弱点をよく知っている。」 |
| |
山川 |
「いろいろあるけど、最後は歌だ。下手でもいい、その存在感が大事だ。それを助けるためにすべてのスタッフがいるのだ。」 |
| ●若い人へ |
| |
金一 |
「若い人と仕事をすると、おまえらに理想はないのかと言いたくなる時がある。」 |
| |
山川 |
「クリエイト大阪の舞台監督の仕事が、システムとして確立してしまったからではないか。」 |
| |
大橋 |
「クリエイトのシステムが確立されてきた精神を理解したら、そのバックボーンが見えてくると思う。出演者に絶対にさからわないというセーフティカードと便利にシステム化されたマニュアルを安全性として守っている。そしてそのウエイトが重くなっている。」 |
| |
長野 |
「クリエイト大阪のシステムやマニュアルというのは、さまざまな事をやってきて無駄な部分がそぎおとされて今の形になった。その形だけでいいのかというのを考えないといけない。時代によって仕事のスタイルは違うが、回顧するのではなく、これからの形を作っていくうえでは、その部分を知っていないと付け加えることもできない。若い人を見たときに、これでいいのかという疑問がある。自分たちは、音楽が好きだからなんとか食えればいいやという気持ちで舞台監督をやってきた。しかしそれが、ちゃんとした商売になった。その後の人たちは商売である事があたりまえになる。」 |
| |
山川 |
「その極端な形がアメリカの制度だと思う。それが、アメリカのショービジネスを成長させた原動力だったのは間違いない。しかし、不向きな人間まで制度の力で守られるという弊害がある。制度には完璧な制度というものはなくて、どこに目をつぶるかという事だと思う。日本だったら、ダメなやつには仕事が来ない。あるいは、調子よく人間関係で渡ってゆくしかない。しかし、アメリカの場合には人間性に関係なく、その場にいればお金になる。いずれにしても、舞台監督は歌手にとっていい弁護士であって欲しい。被告である歌手に、全面的な愛情と信頼を獲得するように努力してほしい。歌手にもいいたい。スタッフは使用人ではない。使用人だというのならクビをきってから言えといいたい。スタッフである以上は、その人の人間性を尊重して使ってほしい。スタッフも、自分は使用人ではないというプライドを持ち続けてほしい。」 |
| |
金一 |
「使用人ではないということは、言い方をかえると自分の哲学をもてるかどうかということだと思う。歌手が何と言おうと、それは違うと言えるかどうかだ。」
|
| |
山川 |
「ボクの立場から言えば『それは違う』とは言えなくてもいいから『ちょっと待ってください』と言って調整に走る、せめてそこまではやってほしい。調整をせずに、歌手の機嫌が悪いからといって、歌手の言ったとおりにしてしまうといい結果にはならない。」 |
| |
大橋 |
「若い頃、ミュージカル「死神」をやった時、主演の西村晃さんがスタッフが悪いと言いだした。その時、舞台上で金一さんがそれは違うでしょという事をはっきりと話をした。自分なりに、なぜそれができるのかと考えた。」
|
| |
金一 |
「それは、ヒエラルキーが歌手にあったらできないいうことだ。仮に演出家がいなければ全体を仕切れるプロデューサーがいることが必要。何をどうしたいのかということがはっきりしていれば成り立つことなのだ。」 |
| |
山川 |
「ヒエラルキーのてっぺんに歌手はいないのだけれど、下から持ち上げてチアリーダーのてっぺんに歌手がいなければとんでもないことになる。それとヒエラルキーは違うということをわかって仕事をしなければならない。」 |
| |
大橋 |
「大道具の人と話をしたときに、最近舞台監督でこの人はと思う人がいるかと聞いたら、“舞台監督?ステージ上でのタレントのマネージャーでしょ”と言われた時はショックだった。多くの人の認識が、舞台監督はステージ上でのタレントのお付きだと思っているという事は事実としてある。」 |
| |
山川 |
「ただ、みんながそうだとは言わないが、仕事のできない舞台監督もいる。タレントが自分のイエスマンを自分への愛情だと思って使っているケースもある。」 |
| |
大橋 |
「これはタレントが言っているから、これは演出が言っているからという事を無意識で言っている人もいる。じゃ、おまえは何かということになる。それは条件反射のようになっている。」
|
| |
長野 |
「今、社内でも金一さんの現場でいっしょに仕事をしている人間が少なくなっている。個々やりかたがちがうので、そのまま引き継ぐこともないと思うが、何を引き継いでいくかということを決めるまでには、まだ時間がかかるのかもしれない。」 |
| |
金一 |
「若い人と一緒に仕事をやってみて感じるのは、時間のかけ方が少なすぎる。おまえほんとに考えているのかと言いたくなるほど、勉強をしていない。いくらやっても、仕事が終わることはないのだ。」 |
| |
山川 |
「自分がなぜクリエイト大阪に机をおかせてもらったかというと、いつどんなに遅くなっても誰かが何かを事務所でやっていたからだ。」 |
| |
金一 |
「どんなステージでも、よくしようと思ったらきりがない。最終的にお金がないからどうしようもないということもあるが、もうすこしエネルギーをかけてやればできることもある。エネルギーをかけてやらないと、仕事がおもしろくないだろうと思う。」 |
| |
山川 |
「金のない部分というのは、手間暇をかけたアイディアであったり、労力で補える部分なのだと思う。」
|
| |
金一 |
「それだけエネルギーをつぎ込むと自分にかえってくるものも大きい。もっと時間をかけたらいいと思う。時間をかければ、それだけ仕事も楽しめると思う。パソコンはいじっているのだけれど、ほんとに考えているのかと、ついつい思いたくなる。僕らの仕事というのは、いかにかかわっているスタッフを、早くやる気にさせるかという事だ。時間をかければかけるほど、考えれば考えるほどいいということがある。終わると、ああ、あそこをこうすれば良かったという事ばかり。これでよかったという仕事は、一度もなかった。」
|
| |
山川 |
「まったく同じでこれがベストだったと思ったことは一度もない。」
|
| |
金一 |
「やることは際限なくある。絶対に仕事がなくなるということは無い。時間を考えてねばる、絶対になんとかできるはずだというねばっこさというのは、時間をかけないと生まれてこない。」 |
| |
大橋 |
「それは、現場感覚というのが薄れてきているからだと思う。人間と人間だから、その場の臭いや空気がある。その感覚がわからないと、現場でなにかあったときにお客さんやアーティストが何求めているかは解らないと思う。現場でトラブルがあったとき、どう対処するかというのが出てこない。お金がなかったら知恵をはたらかせてみるという事から見えてくるものがある。それがないと、マニュアルに走るということが起こってしまう。財産としての人間関係がものすごい豊富だというのは、時間をかけたりたいへんな仕事をしたことによって生まれるのだと思う。ハードな事をやったから人脈や実績、自分の価値観や知恵というのが出来る」 |
| |
長野 |
「経験値で補うということなのだ。しかし、今の子供たちは生まれたときからデジタル。しかしアナログでなければならないことをちゃんとやってかないと、なぜデジタルなのかが解らない。時間の使い方もまったく変わってくる。」 |
| |
山川 |
「舞台はデジタルではできない。ステージは所詮アナログでデジタルにはなりえない。AというポーズからBというポーズにいく途中の時間が大事。そこが表現できるかということ。今の振り付けはAからBへ変わるときにデジタル。人間の何かを表現するという事でいえばデジタルにはできない。」
|
| |
大橋 |
「ライブを見るということはアナログなのだ。歌うのは歌手がやる、つなぎでどう気持ちよくAを終わらせてBをはじめるかのすきまをどうするかによって、立体的に見えるものだ。そこに、スタッフの存在する必要性がある。常に、その時点で必要とされることが変わるだろう。その必要性をリサーチしてゆく事が大事なのだ。ライブというのは、積極的にアナログを楽しむところだというのは、この先も変わらないだろうと思う。ただ、客がそれを意識しているとは思わないが・・・。」
|
| |
山川 |
「舞台監督は、演出家や脚本家と違い能力の差が表にでにくい。能力がないなりに、誠実に手間暇をやることにで補えることはいっぱいある。だから訓練がなりたつと思う。やっぱり、技術とか才能の差はあるが、舞台監督は努力によって追いつける部分はいっぱいある。だから舞台監督とは人間そのものなんだと思う。きっと未来の舞台監督といのは、演出家構成家の代行者、音楽プロデューサーであるところを兼任せざるを得ないだろう。超優秀な舞台監督がいたら、自分より演出家より音楽家よりギャラが高くていいと思っている。それくらい大事な仕事だと思う。テレビのADとはまったく違う仕事だ。テレビという枠の中で、取り直しOKの修羅場をくぐっている人間と、一回きりのところで修羅場をくぐっている連中では違うと思う。そこのところを勘違いしないで若い人に頑張ってほしい。」 |
| |
|
2006年 3月 |
| |
|
文・北爪 努 |
| |
|
|